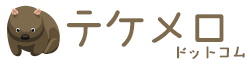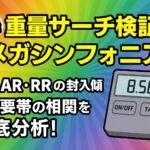| 概要 | 現在までに80万枚以上を売り上げている伝説的なメジャーデビューアルバム。 激しいツーバス、美しいバラード、刹那を匂わせるロックナンバーに派手なシャッフルと、各メンバーの音楽性が反映され見事に調和されている。 本作は、単なるヘヴィメタルアルバムではなく、メロディアスな楽曲と圧倒的な演奏力を兼ね備えた革新的な作品として高く評価されました。 また、Xの後のサウンドの方向性を決定づけた重要な作品でもあります。 |
|---|---|
| ジャンル | ロック・ヘヴィメタル |
| 発売日 | 1989年4月21日 |
| 収録曲数 | 12曲 |
| 収録時間 | 65分12秒 |
| レーベル | CBSソニー |
PROLOGUE (〜WORLD ANTHEM)
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | F.Marino | 編曲 | X |
|---|
静かに幕を開けるピアノとシンセが、まるで“劇場の開演”を告げるようです。
この楽曲は、フランク・マリノの「World Anthem」を引用しており、実はXが“世界”を意識していたことの証拠でもあります。
YOSHIKIの音楽に対するスケール感の大きさを、冒頭から感じ取ることができます。
BLUE BLOOD
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
テンポ188による怒涛のツーバス(いわゆるdkdkdkdk...)から展開されるエグいナンバー。
疾走感のあるリフで一気にギアを上げる、アルバム本編の口火。
YOSHIKIのドラムはまさに爆発。休む間もないツーバス、叩きつけるようなスネア、手数足数ともに極限です。
TAIJIのベースは超高速の展開に食らいつくようにして絡みつき、8ビート基調でもアタックの強さで存在感を放っています。
ギター陣はツイン体制ならではの厚みを活かし、HIDEは鋭く切り裂くようなリフ、PATAは重厚で骨太なリズムを構築。
TOSHIの声も最初から全開で、“音の洪水”という言葉がぴったりの一曲です。
WEEK END
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
LIVEでお馴染みなこの曲は8ビート主体のロックンロールな楽曲。
イントロのメロウなギターと、そこから急転する構成がドラマチック。
Aメロの静けさとサビの爆発力の対比が絶妙で、YOSHIKIの“静と動”を使い分けるアレンジ力が光ります。
95年以降のバージョンではライブでドラムからピアノへ走る演出が印象的でしたが、スタジオ音源ではより整ったバランス感を感じさせます。
TAIJIのベースはメロディの陰に回りながらも、サビではしっかり前に出て、空間を支えています。特にBメロの低音グルーヴは鳥肌モノです。
TOSHIのボーカルは張り上げ型ですが、単なる叫びではなく、ブレスと抑揚が巧みにコントロールされており、繊細な表現力を感じさせます。
EASY FIGHT RAMBLING
| 作詞 | TOSHI&白鳥瞳 | 作曲 | X | 編曲 | X |
|---|
アルバム中でも異色の“陽気ロック”系ナンバー。
YOSHIKIは珍しくスネアを少しラフに鳴らしていて、あえての“抜き”を感じさせるグルーヴ重視のアプローチ。
TAIJIのベースも、跳ねるような動きで、ジャズやブルースの要素を想起させます。
HIDEのソロは遊び心に満ちていて、この曲でのギターは“叫ぶ”より“語る”方向に振り切られています。
歌詞には、「簡単に戦うことに飽きた」というメッセージが込められており、暴力や争いに疲れ果てた人々へのエールが込められています。
X
| 作詞 | 白鳥瞳 | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
Xジャンプ(頭の上で両手をクロスして飛ぶ)でお馴染み、バンドを語る上で欠かせない楽曲。
YOSHIKIの代名詞である全身全霊のツーバスも惜しみなく披露されており、LIVEではファンがガンガン頭を振るヘッドバンキングも恒例行事になっている。
また、音源には収録されていないが、LIVEでは楽曲後半にメンバー紹介を行なっており、その後サビ→Bメロ後にTOSHIが発する【PSYCHEDELIC VIOLENCE CRIME OF VISUAL SHOCK】はHIDEが提案したバンドのキャッチフレーズである。
※ヴィジュアル系というジャンルはこのキャッチフレーズからきているとの説あり
ENDLESS RAIN
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
バンドを代表するピアノ主体のメジャー調バラード楽曲。
当時のヴィジュアルには似つかわしくない(褒め言葉)珠玉の1曲であり、それまでバンドに関心のなかった層にも認知される事となった。
ピアノ主体とは言えギター・ベースの主張も随所で見られ、各パートこれまでの楽曲とはまた違った形でのアプローチが見事にはまっている印象。
特にギターソロパートを支えるベースは絶妙で、当時のベーシストであるTAIJIのセンスが黒く怪しげに輝いているのではないだろうか。
紅
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
代表曲にして、日本のメタル・ヴィジュアル系シーンを変えた金字塔。
バンドの代表曲であるこの楽曲はインディーズの頃より数度のアレンジを繰り返し、現在のバージョンに落ち着いた。
その過程でHIDEとTAIJIの功績は絶大で、YOSHIKIがこの曲をボツにしようとしたところ、TAIJIと加入したばかりのHIDEが『こんないい曲をボツにするのは勿体ない。アレンジするから判断はその後にして欲しい。』と説得し、二人で現在の形に仕上げたと言われている。
楽曲としての最大の特徴はサビの前にギターソロが演奏されており、このソロの中盤ではリズムがハーフタイムとなり、その後のソロからサビまで一気に突き抜けていく展開がより一層サビのインパクトを演出しているのではないだろうか。
尚、現在でも高校野球の応援歌として各校のブラスバンドで演奏されている。
XCLAMATION
| 作詞 | - | 作曲 | HIDE&TAIJI | 編曲 | X |
|---|
2部構成のインストで、前半はギター主体のエスニック調となっており民族楽器(ぽい)リズムにクリーン(ぽい)バッキングの上に空間深めな歪み音を主旋として乗せている感じ(ギターの事分からないので適した表現じゃないかも・・・)。後半はベースのスラップからギターのバッキング→ドラムと徐々にアンサンブルとなっていくハードロック調の仕上がり。リズム主体を意図しているのかやたらとキメが多い印象だが、要所にドラムへディレイをかけている効果なのかしつこさはあまり感じない。
尚、筆者の古ーい記憶では、VISUAL SHOCK Vol.2のMVで某H氏がヘビとガッツリ絡んでいた記憶が・・・
オ●ガスム
| 作詞 | 白鳥瞳 | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
ドラムの【タッドッタドッド タッドッタドッド】というフレーズから始まるこの曲はLIVEでの煽り曲となっており、終了までに20分以上かかる事もあるとかないとか。(※ちなみに音源では3分弱)
というのも、曲の前半(ギターソロ前)と後半の間にリズムループ(一定のリズムを延々とループさせ、そこに生の竿物とTOSHIクンの煽り)を入れ、大将(某Y氏)が客席行ってCO2噴射したりする為。
この曲のギターソロは巨人フリークでお馴染みPATAさんが担当。
尚、伏字にしている事に関してはお察しください。
CELEBRATION
| 作詞 | HIDE | 作曲 | HIDE | 編曲 | X |
|---|
本アルバムでは異彩を放つポップで明るいキャッチーな楽曲。
テーマは『シンデレラ』でMVのストーリーは『ロック嫌いのママン・それに反発する主人公の女の子がいて、魔法使いに扮したHIDEが主人公を夢の中のロックンロールパーティーに連れて行く』というガッチガチの設定があった為、MVを見ない状態でも何となく情景が浮かぶ仕上がりとなっている。(主観です、失敬。)
尚、MVにはメンバー全員出演しており『HIDE→魔法使い・TOSHI→ドライバー・YOSHIKI→シンデレラ・TAIJI→イケイケ外人集団と共にハーレーに乗ってコワイナーする人・PATA→通行人(※アルコール有り)』というファンであれば誰しもが納得するナイスなキャスティング映像である。
ROSE OF PAIN
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
全長11分を超えるこの楽曲は、緻密な楽曲構成と感情豊かな表現が特徴で、シンフォニックロックとメタルの融合が見事に表現されています。
曲は荘厳なオーケストラのイントロから始まり、HIDEとPATAのギターリフ、TAIJIの重厚なベースライン、そしてYOSHIKIの激しいドラムが加わり、息をつかせぬ展開が続きます。各メンバーのテクニカルな演奏が複雑に絡み合い、聴く者を魅了します。
そして、TOSHIのボーカルは、繊細でオペラティックなパッセージから、攻撃的で高音のスクリームまで、感情と力強さに満ちています。
痛みや切望を見事に表現しており、曲のダークでメランコリックなテーマを強調するものとなっています。
UNFINISHED
| 作詞 | YOSHIKI | 作曲 | YOSHIKI | 編曲 | X |
|---|
アルバムを締めくくるピアノ主体のバラード楽曲。
前作Vanishing Visionでは未完成であったが、本作では完成Verとなっている。
また、ROSE&BLOODツアーのフォトグラフィーでTOSHIは『この曲に限っては聴いた人に【さすがTOSHIだ】と思わせられる様なヴォーカリストになりたい』的な事を言っていた記憶が・・・(その本、今手元にないので今度確認します)